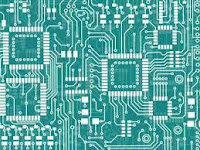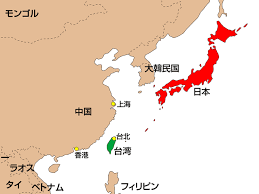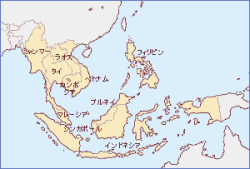ある中国人学者の描く中国の将来(3)

ただ、中国の経済的繁栄がつづくとすれば、将来、若い世代に民主化の求め(「自由」への希求)が生まれるのは、朱建榮氏が展望するように、自然の流れといえそうである。 人は「食べる」ことが充足されこれに飽きるまでになれば、次にはさまざまな「精神の満足」を求めることになる。 「自由」を求める人々は当然ながら画一的統制をきらう。一つの価値観に統一されることをきらう。ひいては強力な一党独裁政治に変化を求めることとなろう。 中国は政治的分岐点に立たされることになる。 人々の求めるものが「強力な統制」と矛盾することに国家指導部も改めて気がつくに違いない。 ただ、自由はともすれば「放らつ」にながされがちである。 経済的、階級的、地域的、文化的、宗教的さまざまな違いを持つ巨大な国に住む人々が、それぞれに自由を求めるとき、 国家の統一維持は困難となり、再び国家分裂の危険性を伴う。かつてのように、衰弱するシシに周辺のどうもうなハイエナたちが狙いを定めることにもなりかねない。自由を求めた「中東の春」が国々にもたらした混乱はいまだおさまっていないのである。 「統制」国家から「自由」国家にどうソフトランディングさせるか、やさしい課題ではない。 西欧的民主主義の基礎には、多数決原理、ボトムアップ原理(民意尊重)、国民の一体性原理(民族融和、人間の平等)などの 基盤思想 があると思う。いずれも「言うは易し生むは難し」である。先進国においては内乱を含む苦難苦闘の長いときを経て定着させていったものであり(トランプ現象をみるとアメリカでさえまだ危うい)、現在後進国がクーデターや内戦によって民主主義定着が一進一退を繰り返している感のあるのも、その獲得に苦戦しているせいであると思われる。 基盤思想の定着は各国にとって歴史的課題であって、即席で獲得できる性質のものではない。中国においては、巨大な人口をもち、多民族国家であるだけに、「民主主義」構築の基盤思想を獲得するのはなおさら、並みの苦労ではないと思われる。ある意味では、世界史上初の挑戦ということになるかもしれない。 長い歴史をもつ偉大な中国人民は、この課題を乗り切るにちがいない。 仮説というより妄想かもしれない。 しかし、この夢のような話は、朱建榮氏などの中国の良心的かつ高い知性から学ぶ隠居老人の切なる願いでもある。(