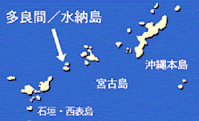「敵基地攻撃能力」米軍指揮下でミサイル飛び交う悲惨な戦争に巻き込まれる!
.jpg)
この12月16日、政府は、敵基地攻撃能力の保有と大幅な軍事費増額などを盛り込んだ安保関連3文書を閣議決定した。 早とちりしてはいけない。これはまだ政府の構想ないし提案にすぎない。これから国会で審議される。関連法案が採決され、予算が可決されないと、ミサイル購入さえその実現にはいたらないのである。 国会審議は来年早々に始まる。閣議決定を「絵に描いた餅」にしなければならない。 老生は、この敵基地攻撃能力について、①戦争の悲惨な拡大、②自衛隊が米軍指揮のもとで翻弄される、この2点を強調したい。 まずは①の点、相互に多数のミサイルを発射し合い、その結果、双方に恐ろしい戦争被害をもたらす点である。専守防衛に反するとか、先制攻撃にあたるといった違法性の次元の思考にとどまってはおれない。 敵基地攻撃手段としての強力なミサイルは、どちらかからひとつ発射されたら、その一発で終わるはずはなく、あっという間に反撃、再反撃ととめどなく発射がつづくことになろう。戦争は質と範囲を越えて拡大し、悲惨な結果をもたらす。 私たちは、ミサイルという「矛」を使用する戦争が、これまでの「盾」による防御に徹した戦争とは大きく様変わりすることに、想像力をこらさなければならない。 今ひとつ②の点である。敵基地攻撃能力の保有は、自衛隊がいよいよ100パーセント米軍指揮下で行動する補完部隊になってしまう、ということである。 12月18日の読売新聞は、敵基地攻撃能力の保有を歓迎したうえで「 反撃能力を行使するには、軍事拠点の把握やミサイルの探知が必要で、これらには米軍の協力が欠かせない。政府は、長射程のミサイル配備を進めるとともに、日米の連携を深めることが大切だ」と書き、危うさの一端をはからずも吐露している。 敵基地攻撃能力を有するミサイルを正確に敵の基地やミサイルにうちこむためには、標的の位置、動きを精密に探知する必要がある。その探知は人工衛星などを使った高度かつ精緻な技術によるほかなく、米軍に頼らざるを得ない。もともと、自衛隊は創立以来、米軍により育成され指導を受けてきた。今度また米国製のミサイルを装備し米軍との共同訓練までしているのである。 米軍が台湾有事などに自らが中心となって立ち向かおうとしているとき、協力者として期待される自衛隊と一体となって効率的に戦闘しようとし、自衛隊の指